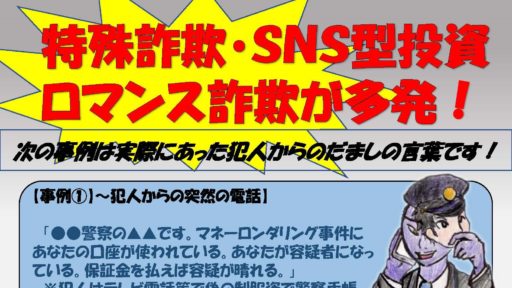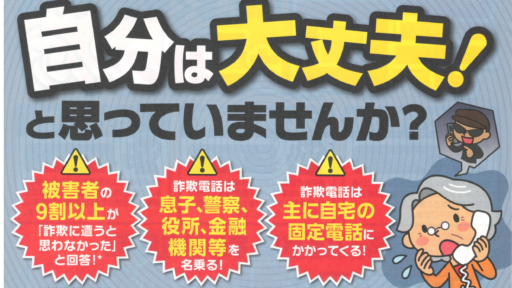ラジオ体操沿革1
2012年9月6日
ラジオ体操の沿革と現状(抜粋)
《なぜ、簡易保険局が、ラジオ体操を作ったのか ?》
1916(大正5年 月)逓信省(郵政省)が簡易保険事業を創設。
(劣悪であった国民の健康状態を改善する事が目的
大正5年当時、民間生保会社の生保契約件数は
約200万件程度、国民の大半は生保の恩恵ない
状態。保健衛生思想は低い、国民病肺結核や伝染
病によって、生活基盤は常に危険状態であった。
目的 ◎国民の経済生活の安定と健康福祉の増進をはかる
事を目的として始められた。
1923( 12年 月)保険事業の調査のため、簡易保険局監査課長
(猪熊貞治氏)が渡米(メトロポリタン社を訪問)
1925(大正14年 月)同企画課長(進藤誠一氏)が再び渡米、メトロポリタン社で実施されている「ラジオ体操」
を実際に見、自分でも滞米中実行してその良さ体験し、帰国後、国内で実施を提唱した。
1927(昭和2年 月)昭和天皇即位の記念事業に「ラジオ体操
を制定する。
1928(昭和3年5月)「ラジオ体操」考案委員会を設立し、体操
の根本を決定した。
(昭和3年11月)東京中央放送局(JOAK)の電波に
乗る。
1929(昭和4年2月11日)全国放送となり、「ラジオ体操の会」
が誕生する。
放送の初代指導者は、江木理一氏(昭和14年5
月まで)
1930(昭和5年 月)東京神田の万世橋警察の児童係担当者(面
高巡査)が夏休み利用して、児童を集めて、児童
の精神面と保険的の両面に良い効果があると考え、
「早起きラジオ体操会」を始めた。




![Meaning of [The friend is pulled to the unlucky affair]. The good luck and daytime are large good lucks in the misfortune and the evening in the morning. However, the funeral is abhorred. Meaning of [The friend is pulled to the unlucky affair]. The good luck and daytime are large good lucks in the misfortune and the evening in the morning. However, the funeral is abhorred.](http://yasato.org/wp-content/plugins/koyomi/image/roku1.gif)